会社概要
- 社名
- 株式会社ICHIZA
- 本社
- 〒874-0834 大分県別府市鶴見3057番地
TEL. 0977-76-9870 FAX. 0977-76-9871
携帯 080-6402-4545
E-MAIL sales@ichiza.net - 別府竹工芸とクラフトショップ ICHIZA
- 〒874-0935 大分県別府市駅前町12-13
B-Passage内
TEL. 0977-84-7789 FAX. 0977-84-7789
リーフレット [PDF]

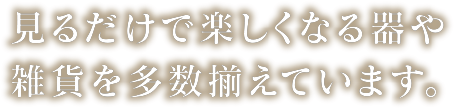
伝統の職人技を受け継ぐ別府竹工芸で、
大地の力強さと美しさを感じる小鹿田焼で、
九州内でつくられたさまざまな工芸品や日用雑貨で-。
お客様のショップを鮮やかに彩ります。
イメージを掴んで頂けるよう、
導入事例をご確認いただける資料を用意しました。
導入のご参考にしていただけると幸いです。